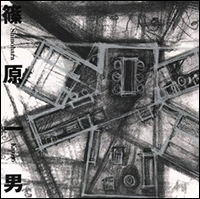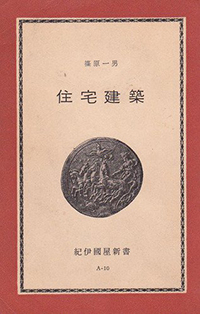| 建築倫理研究06 |
南 泰裕 (敬称略)
|
社会と対峙する手段 天内 このシリーズは「建築理論研究」と銘打っていますが、理論というのは紙のうえで組み立てるため、自分ひとりでコントロールしやすいものです。一方で、現在の建築を取り巻いている状況は、レム・コールハースはそれを「ビッグネス」という概念で肯定的に語ってしまうところがありますが、ひとりの建築家のコントロールを超えた規模を前提としている。そうしたなか、理論というものをどのように位置づけていけばよいのかということが、この企画を立ち上げる際の最初の関心事でした。 今回取り上げる篠原一男さんの場合、住宅によってこそ世の中と対峙できる、世の中に批評を加えられると書かれています。おそらく《白の家》(1966)や《から傘の家》(1961)といった個々の作品でも、そうしたことが展開されていた。前回取り上げたアルド・ロッシであれば、自分の作家としての考え方を社会に向けていく際に、公共建築や複合施設のようなものを考えていたわけですが、篠原さんの場合、住宅というはるかに規模の小さい空間が扱われているわけです。そうした住宅を梃子にして、作家と社会が対峙されている。篠原さんの考え方は、都市や社会から作家が引きこもっていく過程のようにも見えるし、他方、建築家のやれることが限定されていったという意味では、現在につながる動きの始まりだったと捉えることもできるでしょう。 今日は篠原さんの教えを直接的に受けられた坂牛卓さんにお越しいただいたので、やはり住宅のことから伺っていきたいのですが、いま住宅をつくりながら社会に対峙することは可能なのでしょうか。あるいは坂牛さん自身、そうしたことを意識されているのでしょうか。 坂牛 僕は篠原さんから建築を学びましたが、ある時期からちょっと反面教師的に考える部分も出てきました。大学卒業後日建設計に行くことになったわけですが、そのときに伊東豊雄さんに相談したのです。ちょうど伊東さんが《シルバーハット》(1984)を建てられた頃でした。それで「住宅をつくっても社会に対する影響なんてどれほどのものか」なんて偉そうに言ったら、「一戸の住宅が世の中を変えていくんだ」と、すごく怒られました。あたりまえですが、篠原さんもそう思っていたわけですね。 篠原さんはよく「住宅建築というものは写真になって社会に流布しないと存在しないも同じだ」とおっしゃっていました。篠原さんの作品がフォトジェニックにできているのも、そうした理由からです。ただ、そういう理屈が現在も通用するかというと、それは難しいかもしれません。篠原さんが住宅をつくっていた当時は、住宅を建築としてつくっている人など数えるほどしかいなかった。ところが、いまでは新建築でも『住宅特集』なるものができたし、住宅のイメージを流布させる一般誌もたくさんあるわけですね。そうなると一枚の写真が与えるインパクトは、昔ほど大きなものにはなりえないでしょう。 天内 坂牛さんご自身は住宅をつくられて、どのように感じられますか。 坂牛 篠原さんと自分を比較してもあまり意味がないと思いますが、住宅がさまざまな建築のエッセンスであるというのは、共通認識としてあるかもしれません。自分が建築としてやりたいことを凝縮させた何かを住宅ではつくることができるし、それは違うビルディング・タイプにも応用可能である。そういう認識はいまでもあります。 僕が大学に入る前篠原さんと磯崎さんは勉強会をされていたそうです。それはお互いに目指すところが近かったからなのでしょうが、当時、二人のなかで都市が手に負えないものになっていった感覚があったのではないか。磯崎さんはもともと都市をテーマにしていたけれど、あるときから撤退していく。篠原さんにしても、ある時期までは都市に対する興味はあったはずですが、深入りすることなく身を引いていった。 しかし80年代になると、篠原さんは再び「都市の美はカオスにある」ということを言い始める。そうした「カオスの美」と自分の設計とを、篠原さんはなんとか結びつけたいと考えていたはずです。おそらく《東京工業大学百年記念館》(1987)はそういう試みのひとつだし、完成はしませんでしたが「蓼科の別荘」などはスケッチが700枚もあり──『篠原一男』(TOTO出版、1996)の表紙にもなっていますが──、ほとんどカオスと言っていい。それも混沌とした都市の美を住宅につなぎ止める試みだったように思います。 天内 なるほど。篠原さんが「住宅によって社会と対峙する」と言うときに、主体として想定されているのは建築家なのでしょうか、クライアントなのでしょうか。 坂牛 それは建築家でしょう。篠原さんは、建築を設計するうえではクライアントも敷地も関係ないと言っています。バジェットが低ければいい建築はできない、あるいは敷地が悪ければいい建築はできないとなってしまったら、建築家はあまりに無責任ではないかと言うわけです。そこにはクライアントが自分の設計するもののなかに直接コミットしてはこないという前提がある。その辺は僕たちの世代とは違いますよね。 天内 坂牛さんご自身とは違うと。 坂牛 私というか、それは坂本一成さんの世代からすでに違っています。坂本さんの《散田の家》(1969)は篠原さんの《白の家》と同じ60年代後半につくられていますが、いかに《白の家》の嫌なところを直すかという意図が随所に見え隠れしています。《白の家》とプランはほとんど同じであるにもかかわらず、なかに入ると全然違う。《白の家》を換骨奪胎することを狙ってこの家は建てられたのではないかと思うほどです。坂本さんにとっても篠原さんは先生ですが、やはりそこには反面教師的な影響も多少あったような気がします。坂本さんの《代田の町家》(1976)を篠原研究室出身の武田光史さんが観に行ったときに、「この建物には空間がない」と言ったらしいのですが、坂本さんとしては意図してそのようにしたと思うのです。片や篠原さんの住宅の場合、閉じた白い箱があって、どこにも抜けていない。つまり、空間がある。 社会の話に戻すと、70年代以降になると、みんな一度社会的なものから撤退していくのだけれど、その後、再びそこに戻っていく状況があった。先ほども述べたように、篠原さんは建築に「カオスの美」を見出していくようになり、坂本さんも最初は「乾いた空間」と言って閉じた空間をつくっていましたが、社会に対して空間を開いていくようになる。伊東さんもまた、ある時期までは坂本さんと同じような波長で建物をつくっていたように思います。たとえば、坂本さんの《project KO》(1984)は模型を見ると壁がなく、空間が抜けていますが、それは同じころにできた伊東さんの《シルバーハット》(1984)と連動しているように僕らには見えた。さらに言うなら、それは住宅規模のものでも都市へと連続していくのだという意思表示でもあったのではないでしょうか。 南 『住宅論』は、すでに僕が学生の頃にはほとんど伝説の書になっていました。篠原さん自身が半分伝説的な存在になりかかっていて、当時すでに「カオス」や「ランダム」ということを言われていた。60年代から70年代にかけてインテンシヴな住宅をたくさんつくって、それを『住宅論』としてまとめあげて、しかもそこで書かれている内容がものすごく極端でしたから、僕らはみんな驚いたのです。おそらく東工大系列ではない外部の人たちにとってのほうが神話化作用は強く働いたのではないでしょうか。 ところが、今回あらためて読み返してみたら、すごくまっとうなことが書かれていると感じました。「住宅は芸術である」という発言にしても、「住まいは広ければ広いほどいい」とか「敷地は関係ない」という発言にしても、そこだけ取り上げたら傲慢でアーティスティックで独善的なことを言っているように聞こえますが、全体を読み返すと、すごくまっとうなのです。僕からすると篠原さんは極めてまっとうな合理主義者で、作家とも思えないし、さらに言うなら住宅作家とも思えない。建築家として仕事をしていたらたまたま住宅をやることになっただけという感じで、『住宅論』ではなく『建築論』というタイトルでもよかったと思う。時流から離れて作品をつくる孤高の建築家というイメージが篠原さんにはありますが、プレファブリケーションやメタボリズムを含め、当時の建築的状況をめぐるさまざまな問題に、広く言及している。50年代半ばから70年代初頭にかけての高度経済成長期──時期的には朝鮮戦争から大阪万博くらいまでですが、その時代の建築が置かれた状況をきちんと観測しながら、ユニバーサルな建築論を語っていると感じました。 そのうえで、いまこの本を読むことの意味を考えてみたいと思います。現在、埼玉県立近代美術館で「戦後日本住宅伝説」展(2014年7月5日〜8月31日)が開かれていて、篠原さんの《白の家》なども取り上げられていますが、展覧会タイトルに「伝説」と入っていることは象徴的です。伝説化のプロセスに自分たちも加担していることには、功罪があると思うのです。もしかしたら伝説にする必要のないものまで伝説化しているかもしれない。今回、篠原さんの作品集をあらためて見返したのですけれど、作品ではないものを作品化するとか、見せたくないものを見せないような操作を巧みにしているわけです。僕も「戦後日本住宅伝説」展で取り上げられた住宅のうちのいくつかは実物を見ていますが、篠原さんには建築の世界において誰もなしえなかった業績をなしたことに対する敬意があると同時に、不必要な伝説化や神話化が働いていることも認めざるをえない。そうした神話化作用を脱色する必要があるのではないでしょうか。 坂牛 『住宅論』から遡ること6年前の1964年に、篠原さんは『住宅建築』という本を出していますが、『住宅論』に載っている論文のほとんどは、実は64年までに書かれているのです。そういう意味では、『住宅論』にしても『続住宅論』にしても、さまざまな時代のさまざまな論文から厳選して集められている。そうした本の体裁もまっとうに感じられる理由のひとつかもしれません。 南さんは篠原さんのことを合理的とおっしゃいましたが、まったくそのとおりだと思いますね。もともと篠原さんは数学者でしたから、合理的じゃない理屈は許容しない。なのだけれど、どこかでそれをはずしたエキセントリックなところがあって、そこがまた魅力でした。篠原さんのそういうところに対して、坂本さんは「結局、篠原さんは詩人だよね」と言っていたのだと思います。 南 ええ、わかります。昨日も「戦後日本住宅伝説」展を観に行って感じたのですが、《白の家》などは柱梁構造ではないんですよね。フラットな天井の裏面には、水平材としての梁は通っておらず、見えない斜材が屋根の架構をダイナミックに支えている。そのため、全体としては伝統的な軸組構造にはなっておらず、確かにエキセントリックなところがある。 『住宅論』に論理的な一貫性を感じるのは、すべて「カウンター」で、つまり反語的に語っているところがあるからかもしれません。池辺陽が「立体最小限住宅」を発表して「住宅は狭ければ狭いほどいい」と言っていたときに、「住宅は広ければ広いほどいい」と言ったり、要は反対のことを言っている。それでも、不思議なことに篠原さんのほうがまっとうなことを言っているなと感じる部分が多々あるのです。むしろ機能主義者やメタボリストたちのほうが、「社会にコミットする」と言いながら、現実の機微を掴んでおらず、違うんじゃないかと感じることがある。 例えば篠原さんは、『続住宅論』に納められている「都市と住宅のための〈閉じた系〉」という論考の中で、「デザインは社会に対して開かれた系を持つべきだと多くの進歩的なデザイナーや理論家が発言している」と述べ、建築家は個々の建築だけでなく、都市デザインにも積極的にコミットするべきだ、という風潮があると指摘しています(『続住宅論』p.47?51)。その上で、篠原さん自身は逆に、そうした風潮に疑問を持ち、〈開かれた系〉ではなく、独立住宅の設計という〈閉じた系〉を通して、社会と対峙する、というようなことを述べています。 今、これらを読み返すと、そうした篠原さんの言明が、建築家としての手応えと確からしさを、ごくまっとうに伝えてくるような印象をうけるのです。 |
|
|